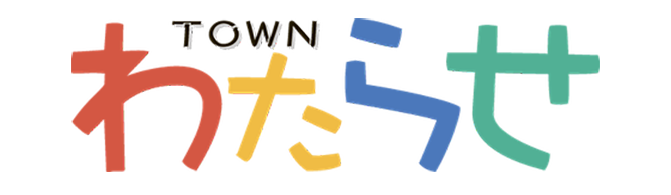4月18日は「よい歯の日」

歯磨き、なんとなく済ませていませんか? 実は、歯ブラシや歯磨き粉の選び方、磨き方ひとつで、歯の健康は大きく変わります。この機会に、自分に合った道具と正しい磨き方を見直してみませんか? 諏訪歯科医院副院長の諏訪渚先生、歯科衛生士の村田夏美さん、山上美穂さんに伺いました。

正しい歯磨きのコツとアイテム選びのポイント
自分に合った歯ブラシ、歯磨き粉の選び方
歯ブラシはヘッドがコンパクトなものを選びます。子どもは子ども用の、サイズの合ったものを使いましょう。毛先のかたさは「ふつう」が適切。「かたい」と歯茎を傷つけてしまうことも。「やわらかい」は歯周病が進行している人向けですが、歯周病が治ってきたら「ふつう」に戻しましょう。
歯ブラシは持ち方も大切。ペンを持つように持つと、毛先が立った状態で歯に当てられます。すぐに毛先が開いてしまう人は、持ち方や持つ手に力が入っているなどの原因で歯に圧がかかりすぎているかもしれません。 歯ブラシを歯に強く当てると毛先が寝てしまうため、歯に毛先がうまく当たっていない可能性があります。歯ブラシの交換の目安は1カ月です。

歯磨き粉はペーストタイプが◯。なるべく研磨剤が入っていないもので、フッ素入りのものがおすすめです。
●正しい歯の磨き方(手順)
どの歯から磨き始めるかの決まりはありませんが、大切なのは磨き残しがないようにすること。そのために、決まった場所から磨きましょう。1、2本ずつ、「今ここを磨いている」と意識して磨くことで、磨き残しを防げます。

〈おすすめの磨き方〉
口の中を、右上・右下・左上・左下と四つのブロックに分けます。1ブロック約1分、奥歯から前歯までは「歯の外側」、一番奥の歯は「歯の奥側」(=写真右下)、一番奥から糸切り歯までは「かむ部分」、奥歯から前歯までは「歯の内側」と工程を意識して磨きます。それぞれのブロックを奥から順番に磨くことで、磨いている場所を意識できます。タイマーをかけ、全部合わせて5分になるよう磨くとよいでしょう。
歯列のカーブ部分(糸切り歯の部分)の磨き残しが多いため、意識して忘れずに磨きましょう。です。
意外と知らない歯の健康に関する疑問
歯に良いの?良くないの? ○×クイズ
炭酸飲料は歯によくないというのは本当?
答えは「◯」

炭酸飲料には「酸(さん)」が入っていて、これが歯の表面(エナメル質)を溶かしてしまいます。特に「リン酸」や「クエン酸」が入っていると、歯が弱くなりやすいです。さらに甘い飲食物にはたくさんの砂糖が入っています。むし歯の原因となるばい菌(むし歯菌)は砂糖を食べて「酸」を出し、それが歯を溶かします。対策としては、酸の多い物を食べたり飲んだりしたあとは、すぐにうがいをすることです。
【出典】日本歯科医師会「子どものむし歯予防」、厚生労働省e–ヘルスネット「酸蝕症」
歯磨き粉を使わずに磨いても歯垢は落とせる?
答えは「◯」
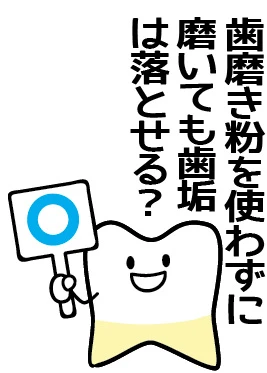
歯ブラシだけでも、むし歯や歯周病の原因になる「歯の汚れ(歯垢=しこう=)」は落とせます。しかし、フッ素(むし歯を防ぐ成分)入りの歯磨き粉を使うことで、フッ素が歯を強くしてむし歯予防に効果があります。歯磨き粉なしでブラッシングしてから、仕上げにフッ素入りの歯磨き粉を使って軽く磨くのがよいでしょう(フッ素を歯に残すために、うがいは1回だけ&少量の水で!)。
【出典】日本歯科医師会「フッ素とむし歯予防」、厚生労働省 e–ヘルスネット「う蝕(むし歯)の予防」
甘いものを食べた後、すぐに歯を磨く方が良い?
答えは「◯」

むし歯は「むし歯菌が砂糖を食べて酸を作り、歯を溶かす」ことでできます。すぐに歯を磨けないと、その酸が長い時間歯を攻撃し続けてしまいます。
むし歯を防ぐためには①ダラダラ食べず、おやつは時間を決めて食べる②食べたらうがいをする。すぐに歯を磨けないときは、口をゆすぐだけでもOK③寝ている間は唾液が減ってむし歯になりやすいため、寝る前は特にしっかり歯磨きをすることが大切です。
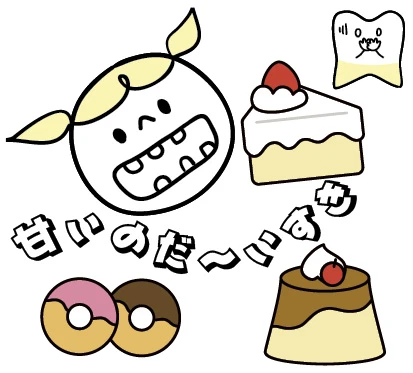
【出典】日本歯科医師会「むし歯の原因と予防」、厚生労働省 e–ヘルスネット「う蝕 (むし歯)」
何を食べたときも、食べたらすぐに歯を磨いた方が良い?
答えは「×」
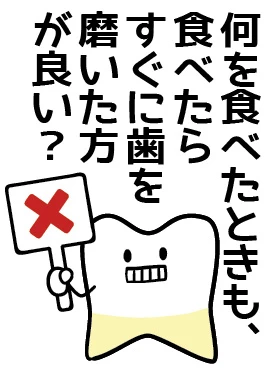
実は「すぐに磨かないほうがいい場合」もあります。
レモン、酢など「酸っぱいもの」を食べた後や、炭酸飲料などを飲んだ後は、歯の表面(エナメル質)が一時的にやわらかくなっているので、すぐに歯磨きをすると削れてしまうことがあります。対策としては、食後30分くらい待ってから磨くこと。その間に「唾液」が歯を守ってくれます。歯磨きではなく、すぐに口をすすぐのはOKです。
すぐに磨いたほうがいいのは普通の食事の後や、甘いものを食べた後。「酸っぱいものの後は30分待つ」「それ以外はすぐに磨いてOK!」と覚えておきましょう。
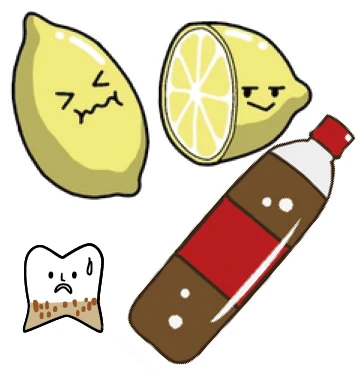
【出典】日本歯科医師会「酸蝕症について」、厚生労働省 e–ヘルスネット「酸触症」蝕 (むし歯)」
電動歯ブラシでないと、 よく磨けない?
答えは「×」
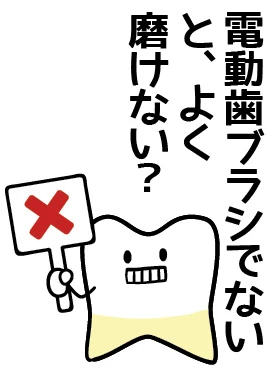
普通の歯ブラシと電動歯ブラシ、どちらも正しく使えばしっかり歯をきれいにできます。電動歯ブラシのメリットは、自動で動くのでゴシゴシしなくてもOK、振動や回転で汚れを落としやすいため短時間でもしっかり磨ける、「歯ぐき近く」や「奥歯」を磨きやすいため磨き残しが減ることです。歯磨きが苦手な人、力を入れすぎてしまう人、効率よく短時間で磨きたい人におすすめです。
普通の歯ブラシのメリットは、歯の形に合わせて自由に動かせるので細かく調整しやすいことが挙げられます。どちらを使う場合も「フロス(糸ようじ)、歯間ブラシ」を併用するとよいでしょう。
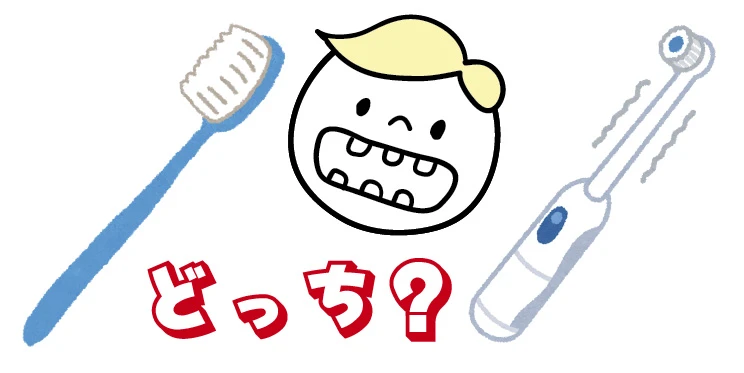
【出典】日本歯科医師会「電動歯ブラシの使い方」、厚生労働省 e–ヘルスネット「歯の健康」
歯垢取りの後、1回の研磨(ポリッシング)で歯は磨耗する?
答えは「×」
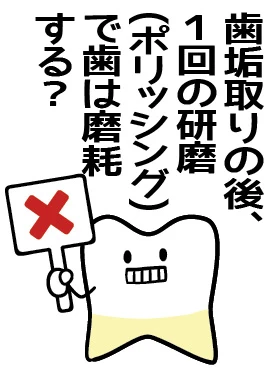
歯医者さんの「歯垢取り」(スケーリング)の後、歯の表面をなめらかにするために「研磨(ポリッシング)」をすることがあります。専用の研磨剤を使って歯の表面についた細かい汚れや着色を取り除くのが目的です。
普通の研磨(ポリッシング)なら、歯がすり減る心配はほとんどありません。歯の表面(エナメル質)はとても硬いため、歯科用の研磨剤で適切に磨く分には問題ありません。むしろ表面をなめらかにすることで、歯垢や着色がつきにくくなるメリットがあります。
しかし、類繁に強い研磨をすると、エナメル質が薄くなることも。歯の表面が傷つくと、知覚過敏(しみる原因)になることもあります。
歯科医院でのクリーニングは適切な頻度で受ける、研磨剤入りの歯みがき粉を使いすぎない(「低研磨タイプ」のものを選ぶのも◎)を心がけ、歯医者さんで相談しながら適切なケアをしましょう。
【出典】日本歯科医師会「歯のクリーニングについて」、厚生労働省 e–ヘルスネット「歯と口の健康」
歯を失う一番の原因は歯周病?
答えは「◯」

日本人が歯を失う原因ランキング(日本歯科医師会調べ)、ダントツの1位は歯周病(約40%)です(他、むし歯が約30%、破折が約15%など)。
歯周病により歯ぐきの炎症が進むと歯を支える骨が溶け、気づかないうちに進行し、気づいたときには手遅れになることもあります。
◆
「痛みがないから大丈夫」は危険!歯周病チェック!(こんな症状があったら要注意!)
①朝起きたとき、ロの中がネバネバする
②歯ぐきが赤く腫れている
③歯ぐきから血が出る(歯磨き中など)
④口臭が強くなった
⑤歯がグラグラする
◆
歯周病を防ぐためには、毎日の歯磨きをしっかりする(フロス、歯間ブラシも使うと◎)、定期的に歯医者さんで検診する、歯ぐきのチェックを習慣にすることが挙げられます。早めのケアが大切です。

【出典】日本歯科医師会「歯を失う原因について」、厚生労働省 e–ヘルスネット「歯周病と全身の健康」スネット「歯と口の健康」
虫歯でないときも、定期的に歯医者さんに行った方がよい?
答えは「◯」
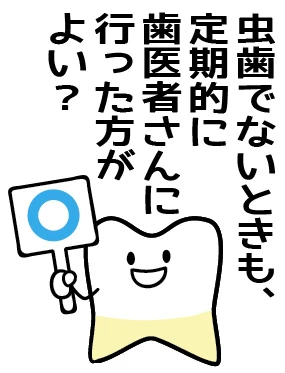
虫歯がなくても定期的に歯科検診を受けるのが大切です。むし歯や歯周病を「早期発見・早期治療」し、痛くなる前に治療すれば削る量も少なくて済みます。
歯磨きでは落とせない汚れである「歯石(しせき)」を歯医者さんでクリーニングすれば、歯周病の予防にもなります。
また、口の中の異変(がんやトラブル)、口の中の粘膜や舌の状態もチェックしてもらえます。
さらに、歯医者さんでフッ素を塗ってもらうとむし歯予防の効果アップ! 定期的な歯科検診は3〜6カ月に1回が目安、歯周病リスクが高い人は1〜3カ月に1回の検診がおすすめです。
【出典】日本歯科医師会「定期健診のすすめ」、厚生労働省 e–ヘルスネット「歯と口の健康」
諏訪歯科医院
桐生市川内町2-236-1
0277・65・7788(祝日は休診/詳しくはホームページをご確認ください)