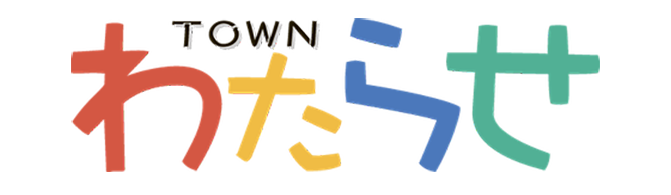県民にこよなく愛される「上毛かるた」。そのゆかりの地をのんびり訪ねる今回は、前橋エリア編です。
上毛かるためぐり
前橋エリアでかるた探し
前橋の養蚕製糸の歴史
前橋市蚕糸記念館
明治45(1912)年に国立原蚕種製造所前橋支所として、前橋市昭和町(当時は岩神町)に建てられ、昭和55(1980)年まで蚕糸試験場として使われていました。昭和56年「糸の町」前橋のシンボルとして後世に残すため、敷島公園ばら園内に移築保存されました。建物の特色としては、エンタシス状の玄関の角柱、れんが積みの基礎、上下開閉式の窓、出入り口のドアの低い取っ手、高い天井など明治末期の代表的な洋風建物で、昭和56年7月に県指定重要文化財となりました。

館内には養蚕・製糸に関する用具・器械などが展示され、蚕糸業とともに歩んできた前橋の近代史を伝える資料館となっています。
群馬県は古くから養蚕・製糸業が盛んでした。安政6(1859)年の横浜開港の頃、生糸が日本の輸出の主要産業の一つでした。さらに需要が増加すると上州の養蚕・製糸業は大いに活気づきます。そして前橋はその中心地となっていき、提糸(さげいと)造り(出荷の形)を「マエバシ」と呼ぶほどであったといわれています。


隣接するばら園の見頃は毎年5月中旬〜6月上旬と、10月中旬〜11月上旬 。春のばら園まつり期間中には座繰(ざぐり)体験(繭から生糸を手でとる体験 )などのイベントも開催します。
開館日/4月から11月の土・日・祝日のみ開館(5月の連休と春と秋のイベント期間中は連日開館)、開館時間/9時〜16時。入館無料。
前橋藩営器械製糸所跡
国道17号「住吉町1」の信号下に長細い石碑があります。これは明治3(1870)年6月に前橋藩がスイス人技師ミューラーとシーベルの2人を指導者として招き、広瀬川を利用した水車を動力源とした「前橋藩営器械製糸所」を創業させた創設地跡の石碑です。
富岡製糸場の開業が明治5年なのでこちらが本当の「日本で最初」となるのですね。創設から3カ月後の9月に本格的な器械製糸工場を現在の岩神町に建設移転していて、そちらにも碑が建立されています。

赤城山
赤城山は標高1828㍍の黒檜山(くろびさん)を主峰に、駒ケ岳、地蔵岳、荒山、鍋割山、鈴ケ岳、長七郎山などからなるカルデラ湖を含む複成火山です。また、日本百名山、関東百名山であり、榛名山、妙義山と並び上毛三山に数えられる名峰です。中央のカルデラの周囲を円頂を持つ1200㍍から1800㍍の峰々が取り囲み、その外側は標高約800㍍までは広く緩やかな裾野の高原台地をなしています。これは富士山に続き日本で2番目の長さです。

中央部のカルデラ内には、カルデラ湖の大沼(おおぬま、おの)や覚満淵(かくまんぶち)、火口湖の小沼(こぬま、この)があります。登山初心者から中級者まで楽しめる豊富な登山コースもあり四季折々の景色を楽しめる観光地となっています。
大沼湖畔
湖畔には1周約1時間半の遊歩道が整備され、夏にはボート遊び、秋にはボートワカサギ釣り、湖面が結氷する冬には氷上ワカサギ釣りが楽しめます。標高が約1350㍍の場所にあり、関東近辺でアイスバブル(湖底の植物が発酵して発生したガスが湖面にたどり着く前に水の中で凍ってしまう現象)が観測できる数少ないスポットの一つです。
赤城神社

赤城大沼の湖畔にたたずむ朱塗りの美しい社殿が特徴の赤城神社。歴史は古く、いくつもの神話や伝説に登場しています。
パワースポットとしても知られており、赤城山と湖の神様「赤城大明神」のもとに召された赤城姫の伝説(「神道集」より)から、この女神さまに願うと女性の願いは必ずかなえられるといわれており、特に女性に人気です。
時折湧き上がる霧にまかれ、沼に浮き上がるように見える社殿は幻想的で、季節や時間ごとにいろんな景色を見せてくれます。
夏と秋の例大祭には、さまざまな神事や催しが開催されます。
※現在、赤城神社へ続く啄木鳥橋は通行できません。
覚満淵(かくまんぶち)

「小尾瀬」とよばれる湿生植物と高山植物の宝庫です。6月中旬〜下旬頃にはレンゲツツジ、初夏には新緑、秋には紅葉、冬は雪景色など、四季折々の自然が楽しめます。
覚満淵を一周(約40分)する木道の遊歩道があり、気軽にハイキングや自然観察が楽しめます。
赤城南面千本桜
みやぎ千本桜の森敷地内の赤城南面千本桜は『さくら名所100選の地』にも選定されるなど群馬県を代表する桜の名所として有名です。満開時には見事な桜のトンネルが見られ、毎年4月に開催される桜まつりには県内外から10万人以上の花見客が訪れています。
また、5月上旬から下旬にかけてはヤマツツジ、9月下旬から10月上旬にかけてはヒガンバナが見ごろとなります。
船津伝次平
天保3(1832)年、原之郷の農家に生まれた伝次平は幼いころから学問に励み、和算の奥義を窮めるとともに研究的に農業を行い農業技術を改良しました。そのかたわら寺小屋の師匠として教育にも努めました。
功績としては安政5(1858)年から3カ年かけて行われた赤城山植林事業や、明治6(1873)年太陽暦が採用され、新暦による農作業日程に慣れていない人々のために作成し配布した、『太陽暦耕作一覧』などが有名です。
また、それらの功績が認められ、明治10年、内務卿・大久保利通から任命を受けて、駒場農学校(東京大学農学部)の教授となります。その後も、農商務省巡回教師となって沖縄県以外の全国各地を巡り、農業技術の普及に努めました。中村直三、奈良専二とともに、「明治の三老農」と呼ばれました。
墓所は、像が建立されている前橋市富士見支所から車で約7分、九十九山の南東にあります。群馬県指定史跡となっています。


公益財団法人 前橋観光コンベンション協会/ 027・235・2211
前橋市教育委員会事務局文化財保護課/ 027・280・6511
赤城神社/ 027・287・8202
前橋市富士見支所/ 027・288・2211