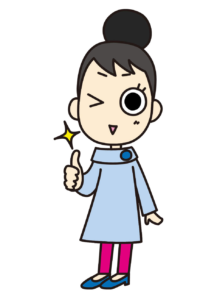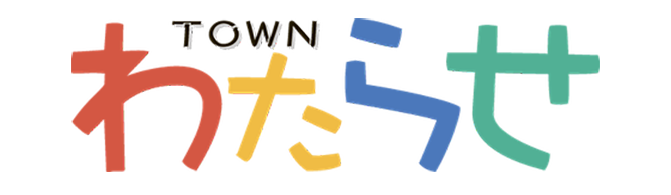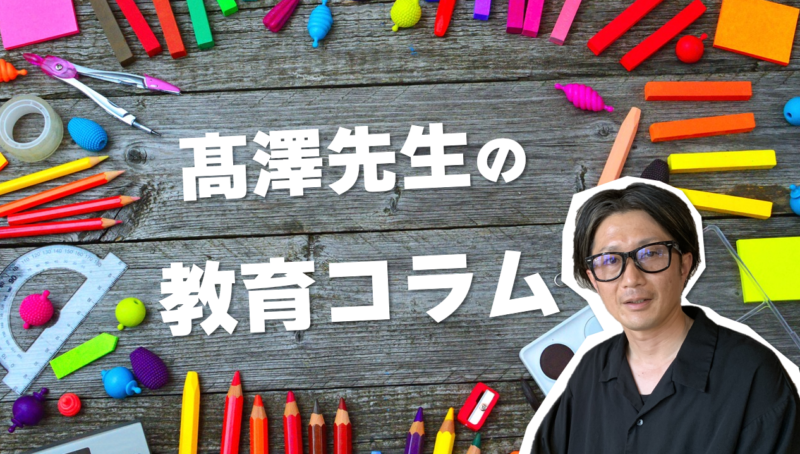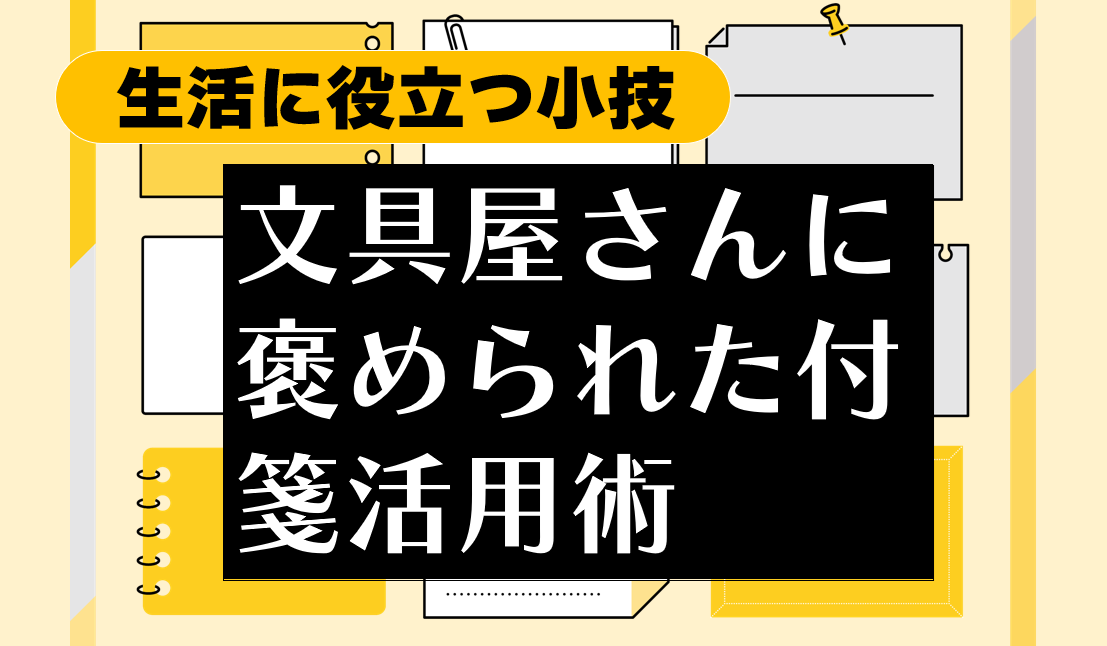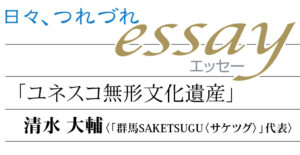
群馬の地酒(日本酒)の情報発信やイベントの企画運営を行っている群馬SAKE TSUGU(サケツグ)の清水です。3回目のエッセーを書かせていただきます。
昨年12月、日本酒や焼酎、泡盛などの日本の「伝統的酒造り」について、ユネスコ無形文化遺産への登録が決定しました。南米パラグアイで開催された政府間委員会の審議での決定で、日本のメディアでも朝4時頃に速報として報道していました。こうじづくりや発酵など、500年以上前に原型が確立した伝統技術が各地の風土に応じて発展し、自然や気候と深く結びつきながら伝承されてきたこと、祭りや儀式など日本文化で不可欠な役割を果たしてきたことが評価されたそうです。私は、日本政府代表の大使が登録決定後のスピーチで、「日本で酒は神々からの贈り物と見なされている」と紹介したことを聞き、律令制時代の「造酒司(みきのつかさ/さけのつかさ)」のように、現代では各酒蔵で蔵人たちが役目を担って神々からの贈り物を醸し、皆に届けているのだなぁなどと思いを巡らせました。これまで長年にわたって働きかけを行ってきた国や酒造関係者の皆さんの地道な取り組みの成果であり、本当に感謝しかありません。
登録が決定した後、ありがたいことに私にも取材をいただきまして、コメントを求められました。雲の上のことで、群馬の地酒にどんな影響があるのかなぁと当初は思っていましたが、やはり伝統的な歴史的意義を世界で評価されたことでメディアに取り上げられる機会も増え、そのことで皆さんが日本酒、地酒を見直して、飲んでみようと思うきっかけになるなと思ったところです。
日本の無形文化遺産はこれまで「能楽」や「和食」「風流踊」などが登録されていて、「伝統的酒造り」で23件目だそうです。今回は自分が関わるものが登録されたことでとても注目したけれど、これまでの22件はどうだったかと考えてしまいました。ニュースになったことは覚えているものの、今回初めて登録を知ったものもありました。そう考えると、今後も引き続き関係者の皆さんと群馬の地酒の評価や価値の発信、PRをし続けなければいけないなと気持ちを新たにしたところです。