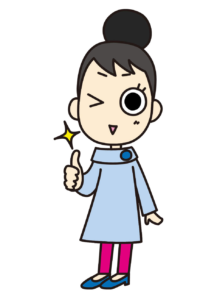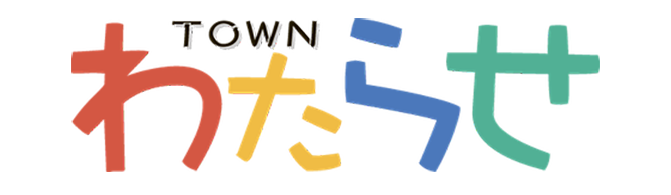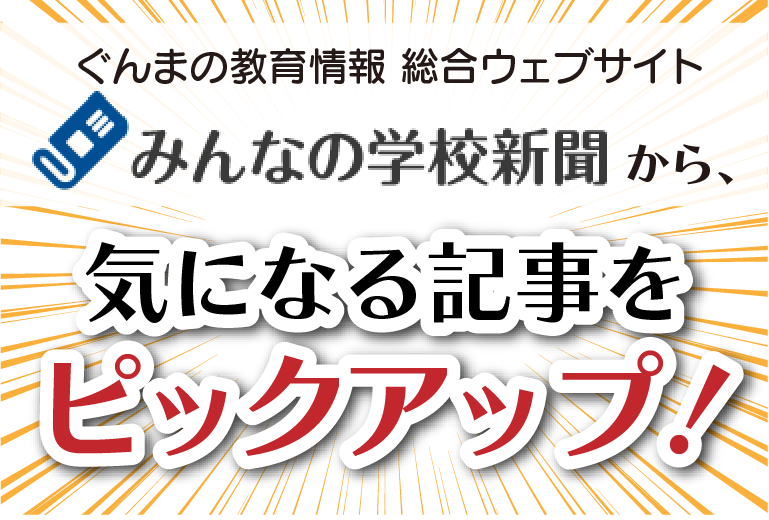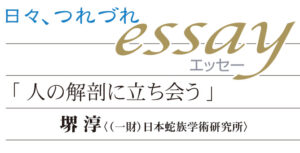
日本蛇族学術研究所に入ってから毒蛇咬傷(こうしょう)に興味を持ち、その研究のためには動物実験も必要で、病理学の知識と技術が不可欠です。その必要性からある大学の医科学研究科の病理学の研究室で学ぶため、2年間休職しました。そこでは組織標本を見るために長時間顕微鏡をのぞいていることが多く、同じ姿勢で顕微鏡をのぞいていると睡魔との戦いは避けられません。夜遅くまで研究室にいるため、学生寮の風呂は終わっているため、いつもこっそりと当直医用の風呂に入っていました。ただ、そこで水虫をもらってしまい、まいりました(もちろん治っています)。また、休職していたため収入はなかったので、食費を節約していたら免疫力が低下し、ケガをしたわけではないのに傷ができ、足のすねの皮下に膿(うみ)がたまってしまいました。病理の勉強に来ていた外科の先生に処置してもらいましたが、研究室でいすに座り、切開するのにメスではなく太い注射針の先で皮膚を切り開き、膿を絞り出しました。もちろん麻酔はしていないので、さすがにかなり痛い思いをしました。膿を絞り出した穴に消毒したガーゼを詰め込み治療してもらいました。その後は学生が行くような食堂で野菜と肉を食べるようにしたら、免疫力が回復して、病気になることはなくなりました。医食同源というようにいかに食事が大切か身をもって知ることができました。
余談が長くなってしまいましたが、本筋に戻ると、病院で患者さんが亡くなると、その死因や病気がどのように広がっているかなど、病理解剖(剖検)して臓器を取り出して調べることがあります。三つの病理学研究室の持ち回りで解剖を担当していて、私も担当の教官の手伝いで、7回ほど解剖に入りました。多くが高齢者で、がんで亡くなった方でしたが、直接の死因は多くが肺炎です。若い女性も1例ありましたが、SLEという自己免疫疾患で、自分の免疫細胞が自分の体を攻撃するというものです。何度も遺体を見ているとつくづく健康の大切さを実感させられました。また、胎児の体内に水分が異常にたまる胎児水腫で流産した症例も経験しました。当然母体には負担が大きく、精神的にもかなり大きな影響があるようです。その後、自分の子どもができたときには、とにかく健康に生まれてきてくれればと願うばかりでした。事故などで亡くなると法医学の研究室で解剖されるのですが、1例交通事故で亡くなった方の解剖が回ってきました。車で衝突した時にハンドルで胸を打ち、心臓につながる太い静脈が切れた症例で、折れた肋骨が血管に穴をあけ、心臓を覆う膜の中に大量に出血した症例でした。この症例ではシートベルトの大切さを痛感することになりました。
現在は毒蛇咬傷という、非常に限られた分野で医療に関わりを持っていますが、医師ではないので、ヘビの判別や毒の作用、診断、治療に関する情報を提供するだけです。ただ、マムシ咬傷だけでも毎年3000件以上起きていて、5人ほどが亡くなっています。重症例も多く、後遺症で何年も苦労されている方がおられます。ヤマカガシ咬傷はまれですが、重症例も死亡例も起きています。限られた分野ですが、多少社会貢献ができているかなと思っています。ただ、あまり収入にはならないので、スネークセンターの運営には貢献できていませんが。