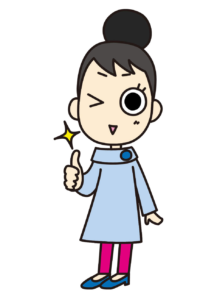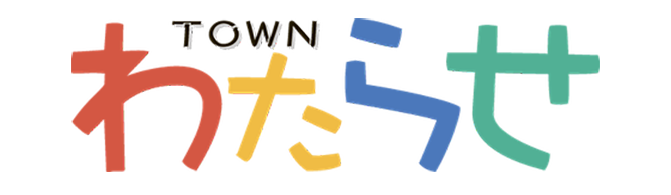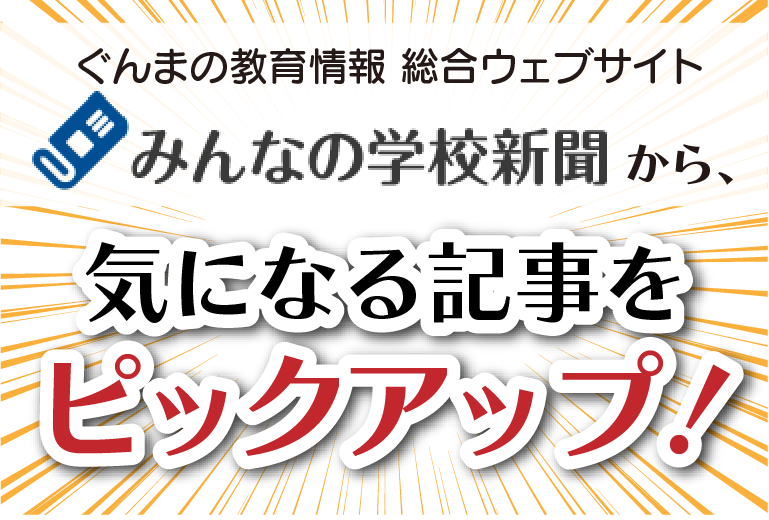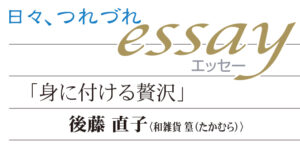
その昔、未婚の子女教育に嫁入り道具として身に付けたこと、身に付けさせられたこと?がありました。
「嫁に行くためには」を大前提の必要不可欠なタスクとでもいうものでしょうか。
裁縫は全女性の必須項目で、私も家庭科という授業で運針からやらされました。
もっとも私の場合は悲惨なものでした。人には向き不向きというものがありどうやってもうまくできないのです。そもそもやる気がないのです、いまだに「ボタンどうやって付けたっけ?」というありさまです。
その他に文化的な素養も茶、華、歌舞音曲などなかなかバラエティー豊かに教養を身につけなくては「嫁に行けない」と世間さまの同調圧力甚だしい時代でございました。
もっともあの当時女性の人生の最終目的は結婚一択、働くなど嫁入り道具の添え物で「キャリアなんぞありえねー」でした(笑)。
ですので当時茶、華、琴、ピアノなどたくさんの稽古事の教室がありました。
研さんに稽古を積み上げてきた名だたるご教授の下に若い女性は弟子入りして稽古に通ったものでした。
今現在そういったお教室は激減しているようです。
社会が女性の社会進出を必要とするようになったからです。時代の趨勢(すうせい)というものでしょうが寂しく残念に思うのは私だけでしょうか?
ちょっと偉そうな物言いをしますが、文化というものは長い時間をかけて連綿と受け継がれ、磨かれ、昇華していくものと思っています。
茶、華は日本文化の最たる様式美だと思います、しかも身近な日常に寄り添ってくれます。
私は茶の素養は全くなのですが、華は親の思惑にまんまとはまり何となく稽古に通い看板を頂くくらいまでは稽古しました。
おかげさまで店の隅に置くくらいなら何とか生けられています。
立原正秋さんという作家の作品で「春の鐘」の一節に「身に付ける贅沢(ぜいたく)」という言葉があります。茶や華などの文化的な素養はこの言葉に尽きると思っています。
現代において茶、華、書、短歌、歌舞音曲は生活にはかかわりません。ですが日本が世界に誇る類いまれな美しい文化です。
年齢や女性、男性にかかわらず贅沢を身に付ける機会があれば、少し勇気を出して触れてみるときっと何かが豊かになっていくご自分に気付けるかもしれません。