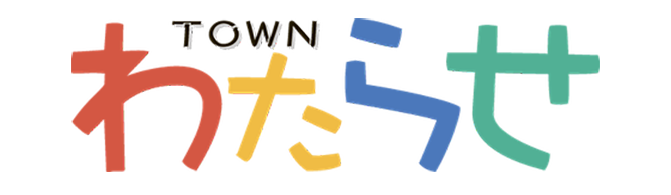2026年度から市内の全小学校58校で開門時間を午前7時に繰り上げるという高崎市の発表が賛否を巻き起こしている。共働きやひとり親家庭の要望に応じた取り組みだが、教職員組合からは「教員の負担増につながる」として撤回を求める声も上がっている。子育て世代の保護者はこの動きをどう受け止めているか、声を拾った。
(2025年8月23日付「みんなの学校新聞」記事から)
高崎市、小学校全校で開門時間を午前7時に前倒しへ
共働き・ひとり親家庭を支援

高崎市は7月、2026年度から市内の小学校全58校で朝の開門時間を午前7時に変更すると発表した。共働き家庭やひとり親家庭から「仕事の都合で早朝に家を出なければならないが、子どもを自宅に置いておけない。学校をもっと早く開けてもらえないか」といった要望が寄せられていたことを受けた対応だ。市によると全国でも数少ない取り組みで、「保護者の勤務状況により早く登校せざるを得ない児童を受け入れることで、家庭の負担軽減につなげたい」としている。
現状では小学校の開門時間は学校ごとに異なり、多くは午前7時30分から50分に設定されている。来年度からは校務員が午前7時に開門し、防犯対策として登校する児童を校門前で見守る予定。校務員には時間外手当を支給して対応する。富岡賢治市長は「共働き家庭などが増える中で、子育てをしながら働く保護者を支援していきたい」と話した。
教職員組合は撤回を要求
一方、この決定に対し、全群馬教職員組合と高崎市教職員組合は8月8日に市と市教委へ撤回を求める要求書を提出。同20日には県庁で記者会見を開き、「児童の安全確保には教員が対応する必要があり、そうなると教員の負担が増える」と訴えた。
保護者世代の反応は?

市の方針を子育て世代はどう受け止めているのか。
高崎市内在住で中学生と高校生の子を持つ50代男性は「基本的には賛成」と話す。「小さな子どもを育てながら働くのは本当に大変なので、その負担を行政が一部でも担ってくれるのはありがたい。ただし、満足度の高い制度にするには教職員の負担増に対する対策も併せて進める必要がある」と指摘した。
同様に、賛成するというみどり市在住の50代女性は「昭和の話になるが、自分の頃は早く登校しても学校は開いていた」と振り返った上で、「現在は何時以降でなければ入ってはいけないと制限されていることに驚いた」という。ただ保護者目線では「遠方へ通勤を余儀なくされている親も多く、子供たちが学校の構内(校庭、体育館含む)にいることで安心材料となる」と話した。「問題点が出てくるかもしれないが、少子化の時代を社会全体で考えることが大切だ」とした。
一方、高崎市内に住む40代の大学講師の女性は「本当に全校で午前7時開門が必要なのか。『先生の手は煩わせないから大丈夫』というのは無責任だ」と批判。教職員組合の主張に同調し、「校務員が対応するだけで済む話ではない。制度として整備し、予算を確保して運営すべきだ」と訴えた。
栃木県内の通信制高校に勤務する50代の女性は、自身のシングルマザーとしての子育て経験を踏まえ、「導入を喜ぶ家庭は確かにある」と理解を示す一方で、「安易に利用する家庭が出てくる可能性がある」と懸念を口にする。「証明書の提出や家庭状況の確認など、利用要件を明確にすべきだ」とした。かつて保育士として勤務した経験から「朝早く預ける家庭はお迎えも遅くなりがちな傾向があった。本当の子育て支援というなら、大人の労働時間に子どもを合わせる社会的な風潮を改善すべきではないか」とも語った。
市教委と教職員組合は、9月に協議の場を設ける予定だ。
(編集部)
本記事は「みんなの学校新聞」で読むことができます
https://np-schools.com/news/15230
[群馬の教育をもっと元気に!]というコンセプトでスタートしたウェブメディア。群馬の教育を元気にすることで、子供たちの未来ももっと明るく、元気になればいいな。そんな思いをこめて運営されています。独自の紙媒体も年2回発行を予定。運営(編集室)は桐生タイムス社が行っています。
→ 「みんなの学校新聞」(https://np-schools.com/)