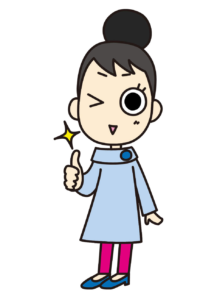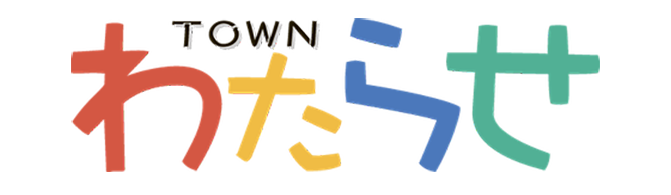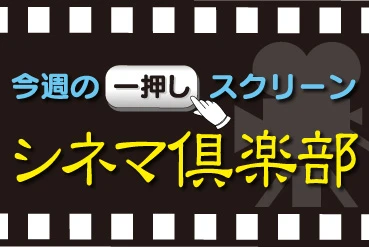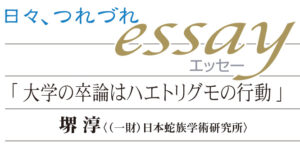
現在は毒蛇咬傷(どくへびこうしょう)の病理(毒蛇に咬〈か〉まれたときになぜこのような変化を起こすのか、それが蛇毒のどのような作用によるのか)を専門にしていますが、大学では生物学を専攻しました(ただ、植物には全く興味が持てず、植物学は非常に苦手でした)。特に動物行動学に興味を持ち、大学の卒論ではハエトリグモの行動について研究を行いました。その頃はようやく日本でも動物行動学という分野が注目され始めた頃です。この分野で一般の人がなじみのあるものは、ミツバチが巣の中で8の字状にダンスをして蜜のある花の方角と距離を伝えるとか、チョウやガが身を守るために羽にある目玉模様で捕食者を驚かすという行動です。今でも新しいことが発見されていて、ある鳥では異なった鳴き声を単語のようにつなぎ合わせて文章のようにして情報を伝達していることがわかっています。どうしてそれがわかるのか。その研究方法(話が長くなるのでここでは省略します)を考えつくこと自体、非常に面白いです。
大学の卒論では、家の周りでもよく見られたシラヒゲハエトリグモを使ってその行動を調べました。このクモは1㌢に満たない小さなクモですが、八つ目のうち、前を向いている二つは大きく、視力が良く、目で見てオスメスを見分けます。
実験のために何匹も捕まえて、オス×オス、メス×メス、オス×メス、さらに大きさを変えて2匹を小さな容器に入れて観察しました。メスは自分より小さな個体はエサと見なして飛びかかる。相手が大きければ逃げる。オス同士も同じです。ただ、オスは相手がメスであれば、自分より大きくても繁殖のために近づかなくてはなりません。そのときに第1肢を広げてダンスをしてメスの攻撃を抑制しながら接近します。それでも時々エサとみなされて飛びかかられますが、それをうまくかわしながら何度も接近を試みます。見ていてとてもけなげに見えます。それではどのようにオス、メスを見分けているのか。メスは大きな目の横にある触肢に白い毛が生えています(名前の由来)。オスではその触肢が精子をためる精のうになっているため黒く丸くなっています。体の模様はほとんど同じなので、オスはその触肢でメスを判別しています。そのメスの触肢を黒く塗ると、オスはそのメスをオスと勘違いして、逃避または捕食しようとします。1㌢に満たないクモで、自分の大きさとどのように比較しているかわかりませんが、1㍉以下の大きさの違いを判別し、攻撃、逃避の判断をするのには驚きます。それともう一つ、エサかどうかはどうしてわかるのか。動きが重要で、動かない物はエサとして認識できません。そこで小さく丸めた綿に糸をつけ、クモの前で動かします。するとエサだと思って飛びかかりますが、かみついた瞬間にエサではないとわかるのか、すぐに放します。その綿に砂糖水を染みこませて実験するとそのままかみついています。このような小さな生きものでも繁殖、捕食のためにわずかな情報で、瞬時に判断して対応し、生き抜いているわけで、つくづく生き物の世界の面白さを感じます。